クロストークの定義:
クロストークとは何を意味するのか、人によって定義が異なります。クロストークという語を辞書で引くと「ラジオ・電話などにおける混線、混信、妨害音、漏話」とあります。2つ以上のチャネルを扱う機材や設備において、ある1チャネルが他のチャネルの信号の影響を受けて、主に他チャネルの信号が漏れてくる現象をさすことのようです。クロストークの代表のひとつは電話における漏話でしょう。クロストークは、ミキサーの性能表示でも使われます。ミキサーは2チャネル以上の多チャネルを同時に扱うので、チャネル間の信号の漏れは可聴範囲をはるかに下回る性能が要求されますが、この時「クロストーク:メインフェーダー間100dB」という風に表記されます。メインフェーダー間というのは実質的にはステレオ2チャネル間のことをさします。似たような言葉にチャネル・セパレーションがあります。セパレーションの語を辞書で引くと、「分離、分割、区分、区別、離別、離脱、隔絶」とあります。セパレートが「もともと1つだったものを分ける」という意味の語であることから、その代表的な例を挙げるとするならば、FMステレオの復調が該当します。FMステレオ信号は、2チャネルの信号を1つの変調信号に変換してから電波に乗せて放送し、受信機側ではこの1つになった変調信号を復調することで元の2チャネルの信号に分離します。従って、FMチューナの性能表示では、この復調における分離能力をさして「ステレオ・セパレーションが何dB」という風に表記されます。もうひとつの代表的な例としては、ステレオLPレコードが挙げられます。ステレオLPレコードでは、2つのチャネルの信号を1本の溝に刻み、カートリッジの1本の針を使って再び2チャネルの信号として取り出しますが、その時にちゃんと2チャネルに戻せる性能をさしてチャネル・セパレーションというからです。
そこでこの2つの言葉ですが、ここでは
クロストークとは「2チャネル以上の信号を独立して扱う機材において、異なるチャネル間で生じる信号の漏れ」をさし、2chステレオシステムにおいては誤解を避けるために左右チャネル間クロストークと呼ぶ、と定義します。
一方、チャネル・セパレーションとは「2チャネル以上の信号が変調などの技術を使って、より少ないチャネルの信号で伝送あるいは記録されたものを、元の複数のチャネルに戻す際の分離性能」をさす
但し、ここでいうクロストークのことをチャネル・セパレーションと呼ぶ場合も多いので、厳密な区別をすべきかどうかはなんとも言えません。民生機では主にチャネル・セパレーションと呼ぶ一方で、業務機材ではクロストークと呼んでいます。しかし、FMステレオの復調性能とアンプのチャネル間の信号の漏れをいっしょくたにしてチャネル・セパレーションと呼ぶことに違和感を覚えるのは私だけではないようです。
考え方:
第2章でクロストーク特性についての基本的な考え方を述べましたが、多くの記事がクロストークに関して感心が薄いと思います。雑誌のアンプ製作記事で、周波数特性や歪み率特性は詳細にレポートされているのに、クロストーク特性を測定・公開しているものは全体の半分にも満たないというのが現状です。音にインパクトを与える要素であるにもかかわらず、あまり関心が払われないのは一体どうしてなのでしょうか。球の銘柄ごとの差し替え比較試聴記事はたくさんありますが、クロストーク特性の改善に努力が払われた形跡のある記事というのはほんとうに少ないと思います。レコーディングをする側は、左右チャネル間のクロストークには非常に神経を使い、また厳密な定位の管理が行われます。一方で、再生する側が定位や左右チャネル間のクロストークに無頓着で上質のオーディオと言えるのかどうかはなはだ疑問です。
もっとも、モノラル構成のプリアンプとメインアンプを2セット作ってステレオで使うのならば、本章で述べるような問題は根本的に解決されてしまいます。
低域の左右チャネル間クロストーク:
低域のクロストーク性能については良くなくてもかまわない、という考え方が主流だったように思います。人の音の方向感覚は低域ほど鈍感であるため、極端なはなしステレオにする必要すらない、という意見もあります。それも一理あるなあと思いつつ、必ずしもそうとは言い切れないのではないか、というのが私の印象です。何故ならば、100Hz以下の左右チャネル間クロストークがよろしくないパワーアンプの性能を改善したところ、みるべき変化があったからです。プロの音響エンジニア達と接触するようになってわかったことは、彼らは低音楽器のプレゼンスに対して非常に敏感であることです。ドラムスのキックやタム、ベースといった楽器の音をどうとらえるかについて常に現場で苦労していて、当然、レコーディングやPAのMIXの結果について耳を澄ませている姿に出会います。彼らの要求を満足するアンプに仕上げるためにはミッド・ロー以下の帯域についての品質が問われます。そういう意味では、中高域よりも低域においてこそクロストーク性能が重要なようなのです。
メインアンプで最も左右チャネル間クロストークが悪化しやすいのはシングル・アンプです。出力段の電源電圧の変動が出力トランスの1次側にもろに影響するからです。たとえば、シングル・アンプにおいて、1つの共通の電源から左右両チャネルに供給した場合どのようなことになるのか考えてみることにします。
1つの左右両チャネルの共通電源とアースの間には、100μFのパスコンが挿入されているとします(世のシングルアンプのほとんどはこのようになっています)。100μFの容量は、100Hz以下では16Ω以上、20Hz以下では80Ω以上のリアクタンスを持ちます。シングルアンプでは、出力管で発生した信号電流は100%電源回路を含むループを流れますから、この100μFのパスコンには両チャネルの信号電流が流れます。ここを流れた信号電流はパスコンのインピーダンスによって、パスコンの両端にも電圧を生じますが、ここで生じた電圧はすなわち反対側のチャネルにも流れ込みます。測定してみるとよくわかりますが、このような回路では1KHzでは70dBくらいの左右チャネル間クロストークが得られていたのに、100Hzでは50〜60dBくらいまで悪化し、10Hzでは30dB〜40dBあたりまで悪化してしまうものです。
この現象は、黒川達夫著「デジタル時代の真空管アンプ」の「7591Aシングル8Wパワーアンプ」(P140〜P153)にみることができます。440μFの大容量のパスコンにもかかわらず、1つの共通電源から左右両チャネルに直接供給しているために、左右チャネル間クロストークは1kHzで80dBもあるのに100Hzでは約60dB、10Hzでは40dBに悪化しています(P151)。
これを改善するために、パスコンの容量を2倍あるいは4倍の大容量にしても、改善は6dBあるいは12dBにしかなりませんから焼け石に水というものです。「電源に400μFの大容量を投入したからクロストークは大丈夫」ということにはなりません。いちばん効果的な方法は、1つの電源からいきなり左右チャネルに供給するのではなく、150Ω以上の抵抗で左右に振り分けてその先に100μFのパスコンを1本ずつ挿入すればよいのです。こんな簡単なことで20Hzでの左右チャネル間クロストークは60dB以上が楽に得られます。
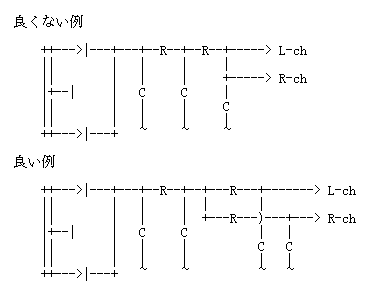
同書の「6GB8シングル14Wパワーアンプ」(P154〜170)では、2つのチョークで左右別個に振り分けているために、10Hzでも80dB以上という素晴らしい特性を得ています。ケーススタディとしての好例だと思います。
低域でのクロストークが悪化する原因のほとんどは電源にあります。2段構成のメインアンプで、初段の電源が出力段と共通になっている場合はもっとひどいことになります。片側の出力段で発生した信号がもろに反対チャネルの初段に飛び込むからです。このような事態にならないためには、初段と出力段は別個にパスコンを用意しなければなりません。要するに、電源に関しては段数分×チャネル分のパスコンが必要なのであり、本来的な機能としてのパスコンを配置することについて決して横着をしてはならないということです。
電源といえば、固定バイアスのマイナス電源も要注意です。安易に1つの電源から左右両チャネルにグリッド・バイアスをかけていないでしょうか。私の「6B4Gシングルアンプ」で、15Hz以下で若干ですが左右チャネル間クロストークの低下が生じていますが、これはバイアス電源を通じての超低域の信号の漏れが原因です。
高域の左右チャネル間クロストーク:
今から20年くらい前のことですが、人に頼まれてLUXのプリアンプのキット「A3400」を組んだことがあります。その時「このアンプは、広い意味でクロストークのことは全く考えていないな。」と思いました。
(1)全段にわたって、1本の双3極管の各ユニットを左右チャネルで使用している。
(2)配線が至るところで左右が近接しており、しかも回路インピーダンスが高い。
(3)すべての電源が、左右共通になっている。(上述の低域の左右チャネル間クロストークの問題)
このA3400は、帯域が狭く、音場の広がりの欠けた、かなり強いLUXサウンドの風味のある、それでいてなんとなく高級感のあるまとまった音のするアンプでどうにも好きになれませんでした。LUX製のプリアンプはいずれも同様の球の使い方をしていますが、どれも揃って似たような特徴のある音を持っているのはこのあたりに秘密がありそうです。
まず、やってはならないことのひとつが「1本の双3極管の各ユニットを左右チャネルで使用」するような構成です。12AX7や6SL7GTのような双3極管では、封入された2つのユニット間にはかなりの浮遊容量が存在します。ここでは「Unit1のプレート→Unit2のプレート」の飛びつきと「Unit1のプレート→Unit2のグリッド」の2種類の飛びつきが複雑に生じます。このような事態がどれほど悲しい結果を生むかは、6SL7GTを左右両チャネルで使用した「6G-A4シングルアンプその1」のクロストーク特性を見ればわかるというものです。
「1本の双3極管の各ユニットを左右チャネルで使用」してもそれほど悪い事態にならない場合というのもあります。そのひとつは、カソード・フォロワ回路の場合です。カソード・フォロワ回路では、プレートが交流的に接地されるので、プレート自体がシールドを同じ効果を生むからです。もうひとつは、第7章でご紹介したように、6DJ8や6CG7のような2ユニット間に管内シールドを持った球を使用した場合です。しかし、いずれの場合でも、ソケットの足まわりの配線には十分な注意が必要です。
12AU7や5687のような低内部抵抗管の場合は、回路インピーダンスが低いおかげで「1本の双3極管の各ユニットを左右チャネルで使用」しても12AX7ほどには浮遊容量による高域での飛びつきは生じません。
部品配置や配線も要注意です。ボリューム・コントロールを出たところでは一般にインピーダンスが高くなりますから、左右チャネルのケーブルを近接させたまま長々と引き回すわけにはゆきません。しかし、線間容量による左右チャネル間の信号の飛びつきは、同レベル同士ではあまり起こりにくいものです。むしろ、一方のチャネルのハイレベルの信号が、もう一方のチャネルのローレベルの増幅段に飛びつくケースが目立ちます。
以下のような部品配置のメインアンプを作った時のことです。シャーシの大きさは25cm×15cm×4cmでかなり小さく、ここにTANGO LH-150と2個のTANGO U-608、2個のブロック・コン、そしてEL34と6FQ7が2本ずつ乗っています。
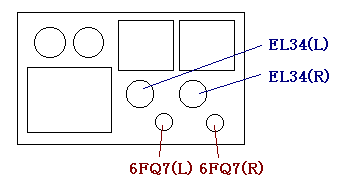
このアンプの左右チャネル間クロストークを測定してみると、「右チャネル→左チャネル」のクロストークだけが、1kHz以上の帯域で周波数が高くなるほどどんどん悪化していました。もしやと思い、「EL34(R)」と「6FQ7(L)」との間にアルミ板を挿入してみると、案の定高域でのクロストークの悪化がすっと改善されました。信号が、右チャネルの出力管「EL34(R)」から空中を伝って左チャネルの電圧増幅管「6FQ7(L)」に飛びついていたわけです。最大出力時には、出力管のプレートからは数百V(p-p)の信号が輻射されるわけでこの威力は相当なものです。
球の配置だけでこれだけ特性が劣化し、はっきりと音に影響を及ぼします。部品配置の変更ができない場合の解決策としては、シールドケースの使用がいいでしょう。しかし、シャーシ内部の配線間の容量の問題は解決できません。回路インピーダンスが低いことは、すぐれた高域のクロストーク特性を得るために非常に重要です。
