2000年を過ぎて制作のデジタル化によるレコーディング事情の変化の影響も見逃せません。1990年以前に制作されたレコーディング・ソースと最近のレコーディング・ソースとでは、低域成分に大きな変化が生じています。アナログ時代はレベル管理そのものがゆるやかで、周波数スペクトルごとのレベル管理はもっぱらエンジニアの勘と経験によっていました。しかし、今日ではPCを使えばきわめて精密なレベル管理が可能になったために、50Hz以下の周波数でいきなりフル・ビットを使い切るようなソースも続々と作られています。こなってくると、100Hz以下の帯域特性が充分でないと、大した音量でもないのにたちまち歪んでしまう、という現象が起きるのです。
負帰還その2 (薬効と副作用)でも述べるように「負帰還は、出来の悪いアンプの出来を良くする、という効果もないわけではない」ですが「もともと周波数特性の悪い増幅回路に負帰還をかけ」てもその効果はかんばしくなく「裸の状態での周波数特性を十分すぎるくらいまで良くしておかなければ意味がない」とさえいうことができます。また、負帰還は出ないパワーを出るようにする効果はありません。負帰還は、1Wにおいて10Hzから50kHzまでフラットにすることはできても、同じアンプで1kHzでは10W出るが100Hzでは5Wしか出ないような低域能力を改善することはできないのです。
低域レスポンスの劣化要因
低域レスポンスの劣化要因を考える場合、以下の2つの視点でとらえる必要があります。
(1)電圧増幅段におけるレスポンスの低下。
(2)電力出力段においてスピーカー駆動のための電流供給能力の低下。
この視点を加味しつつ低域レスポンスの劣化原因を考えてみましょう。
- 段間の結合コンデンサがあるため・・・(1)
- カソード抵抗に並列にはいっているパスコン・・・(1)(2)
- 段間トランスがあるため・・・(1)
- 出力トランスがあるため・・・(2)
- 電源ループの超低域のでインピーダンス上昇があるため・・・(1)(2)
段間の結合コンデンサ
このコンデンサの目的が、前段と後段との間で直流を遮断するという目的であるために、直流だけでなく超低域までカットされるという宿命を背負っています。低域カットの基準周波数は、コンデンサ容量と前後のインピーダンスによって決定されます。
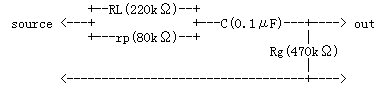 通常の真空管電圧増幅回路では、前段の出力インピーダンスは、その球の内部抵抗(rp)とプレート負荷抵抗(RL)の並列合成値です。内部抵抗80kΩの12AX7のプレートに220kΩの負荷抵抗を与えた場合ですと、出力インピーダンスは、59kΩ=(220kΩ×80kΩ)÷(220kΩ+80kΩ)で求まります(右図)。
通常の真空管電圧増幅回路では、前段の出力インピーダンスは、その球の内部抵抗(rp)とプレート負荷抵抗(RL)の並列合成値です。内部抵抗80kΩの12AX7のプレートに220kΩの負荷抵抗を与えた場合ですと、出力インピーダンスは、59kΩ=(220kΩ×80kΩ)÷(220kΩ+80kΩ)で求まります(右図)。
後段の入力インピーダンスは、後段球のグリッド抵抗(Rg)だけであることが多いですが、この値が470kΩであるとします。結合コンデンサからみると、前段の出力インピーダンスと後段の入力インピーダンスとは直列にみえますので、これを足し算すると、529kΩ=59kΩ+470kΩになります。もし、結合コンデンサ(C)の値が0.1μFであるならば、低域カットの基準周波数は、
f(Hz)=159(定数)÷{抵抗値(kΩ)×容量値(μF)}ですから、
3.0(Hz)=159(定数)÷(529kΩ×0.1μF)となります。3.0Hzで-3dBの減衰です。-1dBの減衰になるのは、基準周波数のおおよそ2倍の6Hzあたり、-0.5dBの減衰になるのが、基準周波数のおおよそ4倍の12Hzあたりです。ということは、10Hzでフラットとしたい場合は、3Hzの設定ではちょっと足りない計算になります。
もっと低域まで帯域を伸ばしたいならば、結合コンデンサの容量を大きくするか、後段の入力インピーダンスを高くします。結合コンデンサの容量を、0.47μFにすれは低域カットの基準周波数は、一気に0.64Hzまで引き下げることができます。
カソード抵抗に並列にはいっているパスコン
カソード抵抗と並列に挿入されるパスコンは、前述の結合コンデンサとはちょっと位置づけが異なります。結合コンデンサでは、ある周波数から下はどんどんレスポンスが低下してゆくのに対して、カソード側のコンデンサでは、ある周波数から下でレスポンスが低下しますが、だいたい3dB〜8dBくらい低下したまま、もっと低い周波数になってもそれ以上は低下しません。なぜならば、カソード抵抗とコンデンサとが並列になっているため、コンデンサのリアクタンスがどんなに増加しても、カソード抵抗値を越えることはないからからです。それでも、カソード抵抗と並列にはいっているパスコンの容量が十分でないアンプと、余裕たっぷりの容量のコンデンサがはいっているアンプとでは、音の仕上がりにずいぶんと違いが出ます。従来、ここには47μF〜100μFくらいのコンデンサを入れるのが常識でしたが、私は経験上それでは足りないと思っています。すくなくとも220μF、できれば470μF〜1000μFくらいを入れてやりたいところです。
ここのコンデンサの値を大きなものに変更することによって、大きな改善効果が得られた(自作)アンプの数は非常に多いのです。コンデンサ1個用意すればすむことですから、実験されることをおすすめします。理由は上手く説明できません。Douglas Self氏によると、アルミ電解コンデンサは低い周波数帯域では容量を余分に与えてやらないと音としてまとまらないそうです。
段間トランス
最近は、インターステージトランスにも、非常に良い特性のものが入手できるようになったため、自作アンプにおいてもトランスドライブがよく採用されます。また、感度の悪い古典直熱3極管を効率良くパワフルにドライブしようとすると、CR結合回路ではさまざまな工夫をしなければならず、設計にかなり高度な技術が要求されますので、むしろ構成が簡単なトランスドライブが好まれて採用されているようです。インターステージトランスも、トランスである以上直流は遮断されます。超低域のレスポンスも良く設計されたCR結合にはかないません。超高域レンジにおける周波数特性の暴れも覚悟しなければなりません。そういった制約の中で、トランスドライブの良さ生かしながら、良好な低域特性が得られるような設計を行わなければなりません。
トランス等の誘導性の信号源には、後段の負荷インピーダンスが低い程、高低ともに周波数特性が良くなる、という性質があります。インターステージトランスの出力側、すなわち出力段のグリッドに抵抗をトランスの2次巻線と平衡に抵抗を挿入するのは、このような効果をねらったものです。しかし、それも度が過ぎると前段の負担が重くなり、時に伝達損失の低下が表面化します。逆に、後段をオープン(つまり抵抗がない)のままにすると、周波数特性としては最も不安定かつ狭帯域となりますが、好んでこのような設定にする場合もないわけではありません。
ところでトランスは、電力を伝達するデバイスでもあります。たとえば、50シングルをフルドライブしようとすると、信号電圧は最大出力時には60Vrmsにもなります。もし、インターステージトランスの2次側と50のグリッドの間に、10kΩのグリッドリーク抵抗があったとすると、この抵抗で消費される電力は、
0.36W = 60V × 60V ÷ 10kΩにもなるわけです。0.36Wの電力を広帯域で伝送するためには、一人前の出力トランス並のコアボリュームが必要です。かなり大型のトランスをおごったとしても、0.36W時に10Hzでコアが飽和しないかというと、ちょっと「?」です。トランスドライブを行おうとする場合は、最大出力時に、インターステージトランスが出力トランスの足を引っ張らないように、出力トランスよりも先にへばらないように考えなければなりません。トランスドライブというのは、一見簡単そうに見えて、実はかなり難しいのです。
出力トランス
出力トランスの低域特性は、コアが直流によって磁化されるかされないか、によって非常に大きな違いが生じます。シングル回路では、1次巻線に流れるプレート電流によってコアの磁化が発生しますが、プッシュプル回路では、1次巻線に流れるプレート電流が磁化を互いに打ち消し合う向きに流れるために、原理的に直流磁化の問題が起きません。従って、シングル用出力トランスとプッシュプル用出力トランスでは構造も異なり、同じではありません(ですから、プッシュプル用出力トランスをシングル回路に流用することはできません)。低域特性は、プッシュプル用出力トランスの方が圧倒的にすぐれています。シングル用の出力トランスに対していかにコアボリュームを投入しても、それなりのサイズのプッシュプル用出力トランスの低域特性を凌ぐことはできません。これは、シングル回路の宿命といっていいでしょう(同じことが、前述のインターステージトランスにもあてはまります)。
さらに低域特性は、出力管の内部抵抗(rp)値の大小によっても影響を受けます。低域が、どの周波数から減衰をはじめるかは、出力トランスの1次インダクタンスと出力管の内部抵抗で決定されるからです。その周波数は以下の式で求めることができます。
f(Hz)={内部抵抗と1次インピーダンスの並列合成値(Ω)}÷{6.28×1次インダクタンス(H)}小型シングル用出力トランス「H-5S」、大型シングル用出力トランス「XE-60-3.5S」、小型プッシュプル用出力トランス「U13-8」、中型プッシュプル用出力トランス「XE-45-8」の4種について比較をしてみましょう。
一目瞭然で、プッシュプル用出力トランスの1次インダクタンスの圧倒的な大きさがおわかりいただけると思います。そして、このことが、1次インダクタンスと出力管の内部抵抗(rp)とで決定される低域時定数の違いに明瞭に表れています。たった0.8kgのプッシュプル用出力トランスの1次インダクタンスが、4.0kgもあるシングル用出力トランスの10倍程度もあるのです。
H-5S XE-60-3.5S U13-8 XE-45-8 シングル シングル プッシュプル プッシュプル 0.8kg 4.0kg 0.8kg 2.3kg 1次インピーダンス 5kΩ 3.5kΩ 8kΩ 8kΩ 1次インダクタンス
(重畳電流)11H〜17H
(50mA)20H〜26H
(80mA)70H〜270H
(アンバランス分2.8mA)230H〜550H
(アンバランス分5mA)ビーム管 6V6 rp=45kΩ 並列合成値 4.5kΩ 3.25kΩ 7.35kΩP-P 7.35kΩP-P 低域時定数 65.1Hz〜42.2Hz 25.9Hz〜19.9Hz 16.7Hz〜4.3Hz 5.1Hz〜2.1Hz 中rp3極出力管 45 rp=1.8kΩ 並列合成値 1.32kΩ 1.19kΩ 2.48kΩP-P 2.48kΩP-P 低域時定数 19.2Hz〜12.4Hz 9.5Hz〜7.3Hz 5.6Hz〜1.5Hz 1.7Hz〜0.7Hz 低rp3極出力管2A3 rp=0.8kΩ 並列合成値 0.69kΩ 0.65kΩ 1.33kΩP-P 1.33kΩP-P 低域時定数 10.0Hz〜6.5Hz 5.2Hz〜4.0Hz 3.0Hz〜0.8Hz 0.9Hz〜0.4Hz
ところで、トランスの1次インダクタンスは、重畳される直流電流が大きくなるほど低下します。シングル用出力トランスの規格において、重畳される直流電流値が規定されているのはそういう理由からです。これを防ぐために、シングル用出力トランスは、直流磁化の弊害が生じにくいような特別な構造となっています。出力を稼ごうとして、出力管のプレート電流をどんどん大きくしてゆくと、一方で、出力トランスの1次インダクタンスの低下を招いて、低域特性は劣化してゆきます。
同じ問題は、プッシュプル用出力トランスにも存在します。そもそも、プッシュプル用出力トランスでは、2本の出力管のプレート電流によって、トランス内部で直流磁化が相互に打ち消されるわけですが、プレート電流値にアンバランスが生じると、やはり、直流磁化の弊害が生じます。そこで、プッシュプル用出力トランスでは、許容できるアンバランス電流値が決められているのです。ちなみに、プッシュプル用出力トランスの低域特性はプレート電流値のアンバランスに対して非常にデリケートで、許容値付近ではすでに相当に劣化していると思ってください。
実際の出力トランスの1次インダクタンスは、さまざまな要因によって変動し、かならずしもカタログ値どおりにはなりません。最大の変動要因は2つあって、ひとつはすでに述べた重畳される直流電流あるいはアンバランス電流です。もうひとつは、伝送される信号レベルの大きさです。信号レベルの大きさによる影響は、プッシュプル用出力トランスにおいてとくに顕著で、小信号時と、大電力時とでは、1次インダクタンスは大きく変化してしまいます。そういう意味で、出力管の内部抵抗と出力トランスの1次インダクタンスによって生じる低域時定数の計算は一筋縄ではゆきません。我々、アマチュアアンプビルダーにできることは、メーカー発表のカタログ値の範囲において、おおよそのところを把握するのがせいぜいだと思います。
電源のインピーダンス
ほとんどの増幅回路では、電源とアースの間に挿入されているデカップリング・コンデンサが、増幅作用における重要な信号経路となっています。従って、電源インピーダンスは、全帯域にわたって可能な限り低いことが望ましいのですが、現実的には、超低域と超高域での電源インピーダンスは上昇するのが普通です。特に低域インピーダンスは、可聴帯域からすでに上昇をはじめることが多く、大きな信号電流が流れるメインアンプの出力段では、帯域特性の劣化の原因になります。この問題を解決する簡単で有効な方策は、電源のデカップリング・コンデンサの容量を大きくすることです。ただし、容量が極端に大きいと、今度は電源ON時の突入電流によって、ダイオードや整流管にダメージを与えることがありますので、注意が必要です。
高域レスポンスの劣化要因
高域レスポンスの劣化要因には、以下のようなものが挙げられます。
- 真空管の入力容量があるため
- 浮遊容量やシールド線の容量があるため
- 段間トランスがあるため
- 出力トランスがあるため
- 電源ループの超高域のでインピーダンス上昇があるため
真空管の入力容量・・・CkとCg-p
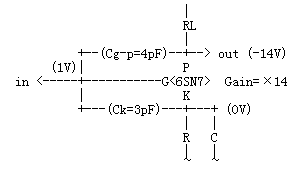 真空管の電極間には、相互に容量が存在します。そのうち、グリッド〜カソード間の容量のことを「Ck」といいます。直熱管では、グリッド〜フィラメント間の容量になるので「Cgf」と表記されることもありますが、Ckと同じ意味です。
真空管の電極間には、相互に容量が存在します。そのうち、グリッド〜カソード間の容量のことを「Ck」といいます。直熱管では、グリッド〜フィラメント間の容量になるので「Cgf」と表記されることもありますが、Ckと同じ意味です。右図のような増幅回路では、カソードとアースの間がコンデンサ(C)でバイパスされているので、Ckは、ちょうどグリッドとアースの間に挿入されたコンデンサのような働きをします。ちなみに、電圧増幅管6SN7GTのCk値は、2つのユニットごとに若干の違いがありますが、おおむね3.0pFです。このとき、前段の出力インピーダンス(Ro)が高いと、RoとCkによるハイ・カット・フィルターが形成され、高域の周波数特性が劣化します。
もうひとつはグリッド〜プレート間容量「Cg-p」です。Cg-pは、ちょっと面白い性質を持っています。右上の図で、今、グリッドに1Vの交流信号が入力されているとします。この信号は、6SN7GTによって増幅され、その利得は14倍であるとします。14倍に増幅された信号は、プレート側に現われますが、グリッドとプレートでは位相は180°回転します(すなわち逆相になる)から、これを-14Vと表現することにします。
さて、グリッドに1Vの信号が与えられた時、4pF容量の向こう側がアースされている場合と、アースされているどころか逆相で-14Vもの信号電圧が生じている場合とでは、どういった違いがでるのでしょうか。
前者の場合は、前述したCkと同じで、グリッド〜アース間の4pFの容量が挿入されたと考えればいいのですが、後者では、4pF×{1-(-14)}=60pFの容量が挿入されたと考えるのです。何故ならば、4pFの容量に流れる信号電流に着目すると、同じ1Vの信号電圧が与えられているにもかかわらず、後者の場合は、前者の場合の15倍もの電流が流れます。ということは、グリッド側から見ると、あたかも4pFの15倍の60pFの容量が挿入されたかのように見えるのです。
この現象を「ミラー効果」と呼びます。ミラー効果による入力容量は、以下の式で計算できます。
ミラー効果=Cg-p ×(グリッド〜プレート間の交流電圧比+1)ここで、「利得」と書かずに「グリッド〜プレート間の交流電圧比」という表現にしたのには意味があります。それは、負帰還がかかった回路では、「利得」と「グリッド〜プレート間の交流電圧比」とが異なってくるからです。そうしますと、このような増幅回路で生じる入力容量の総計は、
入力容量=Ck+{Cg-p×(グリッド〜プレート間の交流電圧比+1)}で求めることができることになります。この値は意外に大きく、アンプの高域特性に大きな影響を及ぼします。入力容量がどの程度になるのか、おおよそのところを以下にまとめてみました。
たとえば、出力インピーダンスの高い5極管6SJ7GTなどで300Bをドライブすると、出力インピーダンスが150kΩであるとして、入力容量は約60pFですから、159000÷150÷60=17.7kHzとなってしまい、17.7kHzで-3dBも減衰してしまうアンプになってしまいます。ところが、ドライバを、出力インピーダンスが8kΩ程度の12AU7に変更すると、159000÷8÷60=331kHzとなって、一気に広帯域アンプの素質を持つことができるようになるのです。
Ck Cg-p グリッド〜プレート間の
交流電圧比入力容量の合計 2A3 7.5pF 16.5pF 3.2〜3.6 60.3pF〜66.9pF 300B 9.0pF 15.0pF 3.0〜3.4 57.0pF〜60.0pF 12AX7/ECC83 1.6pF 1.7pF 60〜70 103.6pF〜120.6pF 12AU7/ECC82 1.6pF/1.8pF 1.5pF 12〜15 19.6pF〜24.3pF 6DJ8 3.3pF/6.0pF 1.4pF 22〜26 34.1pF〜42.4pF 6SN7 2.8pF/3.0pF 3.8pF/4.0pF 14〜16 56.0pF〜67.0pF 5687 4.0pF 4.0pF 12〜16 52.0pF〜68.0pF
また、500kΩのボリュームの後ろに不用意に12AX7の1段増幅回路を持って来てしまったとします。500kΩのボリュームの出力インピーダンスは、0Ω〜125kΩですから、その後ろに120pFの入力容量がぶら下がってしまうと、ボリュームの位置によっては、159000÷125÷120=10.6kHz/-3dBというとんでもない周波数特性になってしまいます。但し、その12AX7に負帰還がかかっている場合は、負帰還の効果によって入力容量は非常に小さくすることができます。
このように、入力容量がアンプの帯域特性の及ぼす影響は、あなどれないものがあります。上記の例では、純粋に真空管内部の容量だけで計算しましたが、実機では、これに線間の浮遊容量やシールド線の容量が加算されるのです。
カソード・フォロワの場合の入力容量・・・CkとCg-p
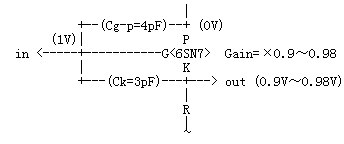 カソード・フォロワ回路では、入力容量が発生するメカニズムが一変します。
カソード・フォロワ回路では、入力容量が発生するメカニズムが一変します。まずCg-pですが、プレート側は電源を通じて交流的にアースされているので、ミラー効果は発生しません。そのため、Cg-pに関する入力容量は、そのままCg-p値になります。
次にCkですが、グリッドに入力された信号は、カソード側にほとんどそのまま同相の電圧が現われます。ですから、Ckには信号電流がほとんど流れません。かりに、カソード・フォロワの利得が0.9倍だとすると、Ckに流れる信号電流は、Ckの一方がアースされている場合に比べて1/10になります。すなわち、グリッド側からはCkの値が1/10になったように見えるのです。ミラー効果の反対の現象が生じるわけです。
そうしますと、このような増幅回路で生じる入力容量の総計は、
入力容量={Ck×(1−グリッド〜カソード間の交流電圧比)}+Cg-pで求めることができることになります。ここでいう「グリッド〜カソード間の交流電圧比」は、通常、0.9〜0.98くらいのいずれかですから、実質的には、入力容量はCg-pの値とほぼ同じになります。入力容量がどの程度になるのか、おおよそのところを以下にまとめてみました。
カソード・フォロワ回路の入力容量がいかに小さいかがおわかりいただけると思います。
Ck グリッド〜プレート間の
交流電圧比Cg-p 入力容量の合計 12AX7/ECC83 1.6pF 約0.98 1.7pF 1.7pF 12AU7/ECC82 1.6pF/1.8pF 約0.95 1.5pF 1.6pF 6DJ8 3.3pF/6.0pF 約0.96 1.4pF 1.6pF 6SN7 2.8pF/3.0pF 約0.95 3.8pF/4.0pF 4.2pF 5687 4.0pF 約0.94 4.0pF 4.2pF
6SJ7GTや6AU6といった出力インピーダンスが極端に高い5極管で、2A3や300Bを直接ドライブしようとすると、入力容量による高域特性の劣化の問題が露呈してしまいます。そんな時、ドライバと出力段の間にカソード・フォロワを挟み込むだけで、「ドライバの出力インピーダンスは高いが、カソード・フォロワの入力容量は非常にに小さい」のと「出力段の入力容量は大きいが、カソード・フォロワの出力インピーダンスは非常に低い」という2つの理由により、トータルの高域特性は一気に改善されるのです(下図)。
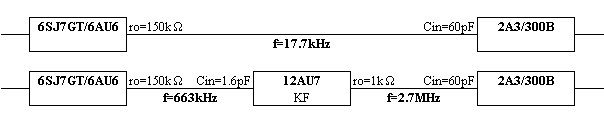
ただし、実装された回路では、線間の浮遊容量、真空管ソケットのピン間の容量などにより、「1.6pF」などということはなくて、「2pF〜数pF」になります。
負帰還がかかっている場合の入力容量・・・CkとCg-p
「真空管の入力容量・・・CkとCg-p」のところで、『負帰還がかかった回路では、「利得」と「グリッド〜プレート間の交流電圧比」とが異なってくる』と書きました。その様子をダイアグラムにしたのが、右下図です。
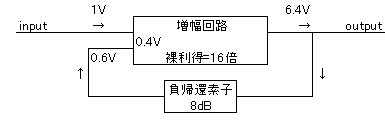 裸利得16倍の増幅回路があって、そこに1Vの信号が入力されています。無帰還であれば、出力側からは16Vの出力信号が現われるはずですが、8dB(2.5倍)の負帰還がかけられているために、出力信号電圧は1/2.5の6.4Vになっています。
裸利得16倍の増幅回路があって、そこに1Vの信号が入力されています。無帰還であれば、出力側からは16Vの出力信号が現われるはずですが、8dB(2.5倍)の負帰還がかけられているために、出力信号電圧は1/2.5の6.4Vになっています。
入力回路のカソードに負帰還が戻されているとすると、入力管のカソードには0.6Vの信号が生じており、実際に、グリッド〜カソード間には、1Vではなくて0.4Vの信号しかかかっていないことになっています。
こういう場合、「グリッド〜プレート間の交流電圧比」は、16倍ではなくて、6.4倍になります。同時に、「グリッド〜カソード間の交流電圧比」も、0.6倍になります。これを式にまとめると、以下のような形になります。
入力容量={Ck×(1−グリッド〜カソード間の交流電圧比)}+{Cg-p×(グリッド〜プレート間の交流電圧比+1)}入力管が6SN7GTであるとして、実際に計算してみましょう。
入力容量={3pF×(1−0.6)}+{4pF×(6.4+1)}=30.8pF同じ条件で計算した6SN7GTの、通常の増幅回路での入力容量は67.0pFでした(前述の表)。ごらんのとおり、負帰還がかかった回路では、入力容量は、Ck、Cg-pともに、ほぼ負帰還量に応じて小さくなっていることがわかります。負帰還は、負帰還ループ内における歪みや周波数特性を改善するだけでなく、負帰還ループの外に対しても、入力容量を小さくできる、という点で周波数特性の改善に効果があるのです。
浮遊容量やシールド線の容量
コンデンサでなくても、配線の線材や真空管ソケットのピンの間に存在する浮遊容量の存在もばかにできません。ことに、シールド線の芯線とシールド被覆との間に存在する容量はかなり大きな値になります。このような浮遊容量は、前述した入力容量の計算で、真空管の電極間の容量に加算して計算しなければなりません。まず、シールド線の容量ですが、一般に1mあたり50pF/m〜250pF/mくらいあります。芯線の被覆に発泡性の樹脂を使った低容量タイプのもので、50pF/m〜100pF/mくらいです。普通に売られている直径3mm〜4mmくらいのビニル被覆のものですと150pF/m〜250pF/mくらいあります。
ということは、低容量タイプで0.5pF/cm〜1.0pF/cm、普通のもので1.5pF/cm〜2.5pF/cmであるということになり、たった10cmの長さでもばかにできない数字になってきます。ましてや、5mも引き回したりすると250pF〜1250pFにもなってしまい、これはもう立派なコンデンサです。
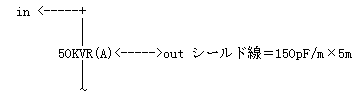 右図のような、ボリュームを使ったシンプルなフェーダーについて考えてみましょう。ボリュームには、50kΩAタイプを使い、メインアンプとは長さ5mのシールドケーブルで接続されているものとします。
右図のような、ボリュームを使ったシンプルなフェーダーについて考えてみましょう。ボリュームには、50kΩAタイプを使い、メインアンプとは長さ5mのシールドケーブルで接続されているものとします。
ボリューム回路の出力インピーダンスは、MAXのとき:0Ω、中点のとき:12.5kΩ(A型の場合は目盛が3時のあたり)、MINのとき:0Ωになります。一方、負荷にはシールド線の容量がぶらさがります。その値が、150pF×5m=750pFであったとします。
ボリュームの目盛が3時頃の時の出力インピーダンスが最大になりますが、この時、ボリュームの出力インピーダンスとシールド線の容量によって構成されるハイ・カット・フィルターの時定数は、
159÷(12.5kΩ×0.075μF)=16.96kHzになります。なんと、17kHzで-3dBの減衰特性になってしまうのです。低容量型のシールドケーブル(70pF/m)を使ったとしても、36.3kHzにしかなりません。実際には、メインアンプ内部の配線にもシールド線が使われているかもしれませんし、メインアンプ初段の入力容量も負荷になってきます。シールド線の容量というのは、全くばかにできないのです。
