しかし、元の信号波形と全く同一で位相だけが反対の波形を得るのは意外に難しく、信号電圧が同じにならなかったり、片側だけ歪みを生じてしまったりするのが普通です。位相反転には、以下で述べるように様々な方式があって、それぞれ一長一短があります。本章では、位相反転回路の基本動作にはじまって、応用回路についても若干触れたいと思っています。
古典型位相反転回路
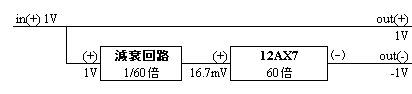 真空管増幅回路では、プレート出力信号は、グリッド入力信号に対して位相が反対になります(増幅回路と位相の章を参照してください)。この原理を素直に利用したのが、古典型位相反転回路と呼ばれる回路です。
真空管増幅回路では、プレート出力信号は、グリッド入力信号に対して位相が反対になります(増幅回路と位相の章を参照してください)。この原理を素直に利用したのが、古典型位相反転回路と呼ばれる回路です。
右図では、2つある出力の一方には入力信号をスルーしてそのまま送り出しています。もう一方の出力には、12AX7を使った一段増幅回路を経た(位相が反対になった)信号を入力します。そのとき、一段増幅回路ではn倍の利得が生じてしまいますので、途中に1/nの減衰回路を挿入して、合計の利得が1倍(=0dB)となるように調整します。
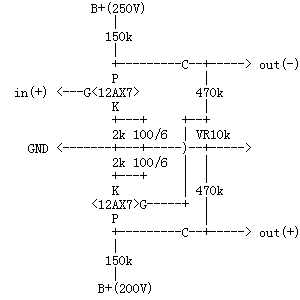 古典型位相反転回路は、通常、前段の増幅回路と対になるように電圧増幅管が選択され、また回路表記されることが多いため、一見プッシュプル回路のように見えますが、実態はそうではありません。
古典型位相反転回路は、通常、前段の増幅回路と対になるように電圧増幅管が選択され、また回路表記されることが多いため、一見プッシュプル回路のように見えますが、実態はそうではありません。
右の回路図では、上側の12AX7は、位相反転回路の前段であって、位相反転の動作には関係がありません。前段のプレート出力信号は、そのまま片側の出力管のグリッドに送り込まれます・・・out(−)。
その信号は、470kΩと10kΩVRとで減衰されて、下側の12AX7のグリッドに送り込まれます。下側の12AX7のプレート出力信号は・・・ここで位相が反転されたわけですが・・・もう一方の出力管のグリッドに送り込まれます・・・out(+)。
ですから、前段管と位相反転管とは、必ず同じ球でなければならないという必然性はないわけです。実際、この回路が登場した頃は、前段管と位相反転管とは異なる球が選ばれていました。ただし、同じ球を使うことによって、出力段に対するドライバとしての出力インピーダンスを同じにできる、というメリットはあります。
また、下側に対応する出力管に送り込まれる信号には、位相反転管で生じたノイズや歪みが二重に付加されることになりますし、周波数特性も相応に劣化することは避けられません。この方式では、精度の高い位相反転動作は望めないということになり、プッシュプル回路の良いところの多くが失われます。
バランス型位相反転回路
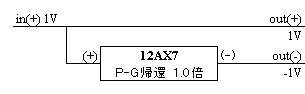 バランス型位相反転回路の原理は、基本的に前述した古典型位相反転回路と同じです。
バランス型位相反転回路の原理は、基本的に前述した古典型位相反転回路と同じです。
違う点は、位相反転を行う一段増幅回路に工夫を加えたことで利得が1.0倍(=0dB)になっているため、途中の1/nの減衰回路が不要になったことです(右図)。
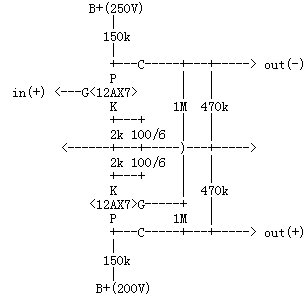 右下の回路図でも、上側の12AX7は、位相反転回路の前段であって、位相反転の動作には関係がありません。前段のプレート出力信号は、そのまま片側の出力管のグリッドに送り込まれます・・・out(-)。
右下の回路図でも、上側の12AX7は、位相反転回路の前段であって、位相反転の動作には関係がありません。前段のプレート出力信号は、そのまま片側の出力管のグリッドに送り込まれます・・・out(-)。
その信号は、下側の12AX7のグリッドに送り込まれますが、下側の12AX7には、2つの1MΩによってP-G帰還がかけられているのがおわかりいただけるでしょうか。P-G帰還では、2つの帰還抵抗の値が同じで、裸利得が十分高い場合の帰還後の利得は1.0倍に収束します。従って、ほぼ同じ信号電圧で、位相が反転された信号がもう一方の出力管のグリッドに送り込まれます・・・out(+)。
帰還後の利得を精密に1.0倍とするには、1MΩのどちらか一方を増減してやります。また、位相反転回路には多量の負帰還がかかっているため、下側に対応する出力管に送り込まれる信号に付加されるノイズや歪みは、古典型位相反転回路よりもずいぶん少なくなります。
もちろん、バランス型位相反転回路においても、前段管と位相反転管とは、必ず同じ球でなければならないという必然性はありません。実際、同じ球を使ったとしても、出力段に対するドライバとしての出力インピーダンスは同じにはなりません。何故なら、位相反転管には特別に多量の負帰還がかけられているため、こちら側の出力インピーダンスの方が極端に低くなっているからです。そのために、前段の出力インピーダンスと出力管の入力容量で生じる高域時定数に著しい差が生じます。古典型の欠点を解決したように見えて別の欠点が増えています。
なお、この位相反転回路と同じ考え方の回路はなんと現代のプロ・オーディオでも使われています。audio-technicaの業務用コンデンサ・マイクロフォンの平衡出力アンプ(真空管ではなく半導体を使っていますが)はこれなのです。また、実に多くのプロオーディオ機器の平衡出力回路がこの方式を採用しています。
P-K分割型位相反転回路
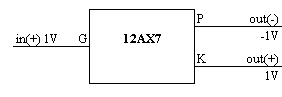 真空管増幅回路では、グリッドに入力された信号に対して、カソード側出力信号は同相、プレート側出力信号は逆相となることを利用した位相反転回路が、P-K分割型位相反転回路です。
真空管増幅回路では、グリッドに入力された信号に対して、カソード側出力信号は同相、プレート側出力信号は逆相となることを利用した位相反転回路が、P-K分割型位相反転回路です。
プレートとカソードそれぞれから、入力信号と同じ信号電圧、つまり利得が1.0倍(=0dB)で、互いに位相が反対となるような2つの出力が得られる回路です。
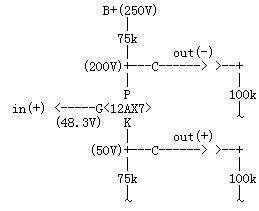 まず、カソード側から信号を得るために、カソードとアースとの間に負荷抵抗を挿入します。こうすることで、この回路はカソード・フォロワとして動作するようになり、カソード側からは、入力信号と同相で、利得がほぼ1.0倍の出力信号が得られるようになります。
まず、カソード側から信号を得るために、カソードとアースとの間に負荷抵抗を挿入します。こうすることで、この回路はカソード・フォロワとして動作するようになり、カソード側からは、入力信号と同相で、利得がほぼ1.0倍の出力信号が得られるようになります。
同時に、プレート側にも、カソード側と同じ抵抗値を持った負荷抵抗を挿入します。この場合、カソード側の負荷抵抗とプレート側の負荷抵抗には、常に(全く)同じ電流が流れることに着目します。カソード電流が1mAならばプレート電流も1mAであり、カソード電流が0.1mA増加すればプレート電流も0.1mA増加します。すなわち、カソード側負荷抵抗に生じる出力電圧と、プレート側負荷抵抗に生じる出力電圧の絶対値は同じであるわけです。ただし、カソード電流が増加した時のカソード電位は上昇しますが、プレート電流が増加した時のプレート電位は下降します。その結果、位相が反対の信号が得られるわけです。
このとき、カソード側の出力インピーダンスは低く、プレート側のインピーダンスは高いため、2つの出力電圧がアンバランスになりはしないか、という懸念があります。
この問題を、右上の回路で考えてみます。カソード側出力に100kΩの負荷を与え、プレート側出力にも100kΩの負荷を与えます。すると今度は、カソード側の交流負荷インピーダンスは約43kΩになりますが、プレート側の交流負荷インピーダンスも同じ約43kΩになるため、やはり、2つの出力電圧は同じになってしまうのです。この自己バランス作用は、出力管の入力容量の影響についても同様です。
ただし、出力管にグリッド電流が流れたような場合は、そもそもグリッド電流は交流波形上非対称であるため、このような2つの出力のバランス効果が生じることはなく、プレート側出力信号が先に歪みはじめます。
P-K分割型位相反転回路を設計する時は、2つの負荷抵抗の直列合成値を使ってロードラインを引きます。動作ポイントの設定も、バイアス電圧の決定も、あたかも1つの負荷抵抗だけであると思って決定します。得られる最大出力電圧についても同様に考えますが、プレートとカソードそれぞれの出力から得られる最大出力電圧は、ここで求めた値の1/2になります。
この位相反転回路の長所は、回路がシンプルであることと、グリッド電位がかなり高く、前段のプレート電位と合わせやすいため、前段との直結回路にしやすいことがあげられます。
短所としては、1つの電源電圧から2つの出力を取り出すため、取り出すことのできる最大出力電圧が、通常の増幅回路の半分程度しかない、という点です。従って、高い入力信号を必要とする2A3や300Bといった出力管を、P-K分割型位相反転回路でドライブすることはほとんどできない、といっていいでしょう。この位相反転回路は、6BQ5や6G-B8のような入力感度の高い出力管のドライブに向いています。
差動型位相反転回路(ムラード型相反転回路)
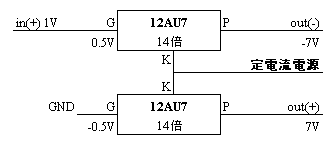 2つの真空管(トランジスタでもよい)のカソード同士を接続し、共通化されたカソードに流れる電流を一定にするような回路(定電流回路)にしてやると、一方のカソード電流が増加すれば、もう一方のカソード電流は増えたのと同じ分だけ減少するようになります。このような回路のことを差動回路といいます。共通カソード側を、定電流回路にしなくても、十分に大きな値の抵抗を与えるだけでも、差動回路として動作します。
2つの真空管(トランジスタでもよい)のカソード同士を接続し、共通化されたカソードに流れる電流を一定にするような回路(定電流回路)にしてやると、一方のカソード電流が増加すれば、もう一方のカソード電流は増えたのと同じ分だけ減少するようになります。このような回路のことを差動回路といいます。共通カソード側を、定電流回路にしなくても、十分に大きな値の抵抗を与えるだけでも、差動回路として動作します。このような回路において、一方の真空管に信号を入力してやると、そちら側の真空管が増幅作用を営むことによってプレート電流が増えたり減ったりします。すると、反対側の真空管のプレート電流は反対の動作、すなわちシーソーのように減ったり増えたりすることになります。その結果、2つのプレートからは、互いに反対の位相で、同じ電圧の信号が出力されることになるのです。
差動型の位相反転回路のロードラインの引き方ですが、ロードラインで使用する電源電圧は、電源供給電圧からカソード電圧を引いたものになります。共通カソードとアースの間の電圧は計算には入れないということです。また、利得の計算では、カソードがアースされているものと考えます。共通カソード抵抗の値は、利得の計算には一切影響がありません。カソード側に大きな値の抵抗が入っているからほとんど利得がない、という記事がありましたがとんでもない誤りです。
ご注意いただきたいのは、入力信号は、直列になった2つの球のグリッドに与えられるため、1つの球あたりの入力信号電圧は、それぞれ1/2になるということです。そのため、一見して、片側あたりの利得が半分になったように見えます。
この原理を使った位相反転回路として最も知られているのが、ムラード(マラード)型位相反転回路です。ムラード型位相反転回路では、共通カソード側は1本の抵抗が挿入されているため、定電流性能には若干劣りますが、それでも十分に実用的な位相反転機能を実現しています(下図左)。
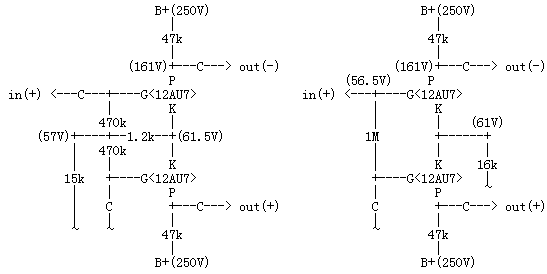
ところで、みなさんが普段見慣れている回路図は、このようなものではなくて、上図右のようになっているのではないでしょうか。すなわち、上側球は、前段のプレートと直結されていているために、共通カソード側のバイアス抵抗が不要になった回路です。ムラード型位相反転回路のオリジナルは、さきにご紹介したようなカソードバイアス方式でしたが、後に、前段直結方式が出現するに及んで、よりシンプルな直結方式が好んで採用されるようになりました。
この回路で重要なのは、2つのカソードが共通化されているということと、共通カソードが15kΩというかなり大きな抵抗によってアースから浮かされているということにあります。この共通カソード抵抗の値が小さいと、有効な差動動作が得られません。有効な差動動作が得られないと、2つの出力電圧にアンバランスが生じます。アンバランスは、下側の出力が低下するというかたちで現われます。アンバランスは、以下の式で求めることができます。
アンバランス(m) = { 内部抵抗(rp)+交流負荷抵抗(RL) } ÷ { ( 1+μ )×共通カソード抵抗(Rk) }上下のアンバランスは、内部抵抗が低いほど、μが大きいほど小さくなるので、LUXは12AU7や6FQ7ではなく、6DT8(特性は12AT7と同じ)を採用しています。生じたアンバランスを修正するには、下側管のプレート負荷抵抗の値を若干大きくします。ここに、半固定抵抗を挿入したり、数kΩの抵抗を追加した回路が多いと思いますが、これはアンバランスの修正のためのしかけです。
共通カソード抵抗の値をどんどん大きくすることによって、この回路の位相反転精度を高めることができます。しかし、この抵抗値を大きくすればするほど、抵抗における電圧降下が大きくなってしまって、有効に使える電源電圧が減ってしまいます。本来、共通カソード抵抗は定電流回路であるべきものです。そこで、ここに定電流ダイオード(CRD)を挿入する、ということが考えられます(下図)。ただし、高耐圧で数百mW以上の電力に耐えられる定電流ダイオードは入手が困難です。高耐圧で大きな電力に耐えられるような定電流素子はないものでしょうか。
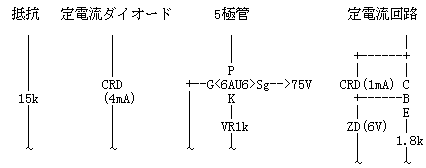
実は、5極管自身が定電流特性を持っています。ここに6AU6のような5極管をあてはめるだけで、立派な定電流回路が実現できるのです。もっと大きな電流が必要な場合は、6CL6、12BY7、6AQ5、6V6、6L6といった5極管やビーム管を使うことができます。また、同じ定電流回路をトランジスタで組むならば、トランジスタ、定電流ダイオード(CRD)、ツェナダイオード(ZD)、抵抗各1個ずつそろえることで簡単に組み上げることができます。共通カソード側を定電流化するだけで、アンバランスのないきわめて精度の高い位相反転回路とすることができますから、是非、おためしになることをおすすめします。なお、定電流回路については、24.1.定電流回路に詳しい説明があります。
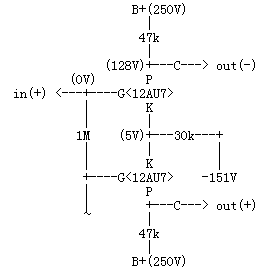 6AH4GT全段差動プッシュプル・アンプでは、初段とドライバ段に定電流ダイオード、出力段にトランジスタ式の定電流回路を使っています。全段差動PPアンプでは、初段でいきなり位相反転を行います。こうするとで初段で発生する僅かな2次歪みすら排除して優れた直線性を得ています。
6AH4GT全段差動プッシュプル・アンプでは、初段とドライバ段に定電流ダイオード、出力段にトランジスタ式の定電流回路を使っています。全段差動PPアンプでは、初段でいきなり位相反転を行います。こうするとで初段で発生する僅かな2次歪みすら排除して優れた直線性を得ています。
また、「デジタル時代の真空管アンプ完全製作12例」(黒川達夫著/誠文堂新光社)では、5極管による定電流回路の好例が多くみられますので参考にされたらいいでしょう。
ところで、この差動型位相反転回路は、非常にすぐれた位相反転能力を持ちながら、アースと共通カソード間の電圧が無駄になるため、どうしても得られる最大出力電圧の上限が制限されがちですが、この問題は、マイナス電源を使うことによって容易に解決することができます(右図)。
グリッド電位に着目してください。これまでの例では、グリッド電位がアースに対して数十V高く設定されていましたが、この例ではアースと同電位(0V)になっています。そのため、有効に使える電源電圧が目減りすることなく、フルに活用できるような電圧配分にすることができました。これならば、2A3や300Bといった、高い入力信号を要求する直熱3極出力管であっても、余裕をもってドライブすることができます。
さらに、共通カソード抵抗の値も大きく(30kΩ)するのが容易になったため、生じるアンバランスを抑えることができるようになりました。
下側管のグリッドとアースとの間に挿入されていたコンデンサ(C)も不要になっています。このコンデンサの絶縁がわずかでも低下してしまうと、2つの位相反転管のバイアスが狂ってしまい、動作が揃わなくなってしまいます。実際、フィルムコンデンサの絶縁劣化トラブルは非常に多いので注意してください。
